|
2日目の朝は、私一人8時起床・9時15分頃に宿出発。ロビーを出てから、路面が濡れ小雨がちらほら降っているのに気付いた。天気が崩れる事は予報で知っていたものの、傘を持たず彦根入りしている・・・。あまり気になる降り方ではなく、きっと大丈夫だろうと、傘は調達せずそのまま足早に駅前お城通りを歩き、内濠をこえて表門へ。 |
| 雨の日のひこにゃんは、お城の表門奥にある彦根城博物館でお客様をお迎えする。 博物館のドコまでがチケット無しでも入れるのか判らないので、玄関からおそるおそる中を覗き込む。見える範囲ではひこにゃんの姿はない。 もしやお城前の天守前広場でお迎えをしているのかと思い、チケットブースでお得なセット券1,400円を購入。このチケットは彦根城域(天守・天秤櫓・西の丸三重櫓・太鼓門櫓・玄宮園・開国記念館)と彦根城博物館が見学できるようになっていて、彦根城と開国記念館に関してはそれぞれを1回づつ観ることも、どちらか2回観ることも可能という優れもの。 なにげなく、ブースのお姉さんにひこにゃんの行方を聞くと「今日は一日そこの博物館にいますよ」と教えてもらい、改めて博物館に向かうと・・・  さっき覗いた玄関で出迎えてくれました(笑) ひこにゃんを見てすっかり壊れた私は急いでスリッパに履き替え、飛ぶようにしてひこにゃんの元へ。 「東京から来たよー!」とテンションの上がった私を快く迎え入れてくれたひこにゃんは相変わらずもふもふした毛並みにつぶらな瞳と白いお顔、そして真ん丸なお腹。とてもとてもキュート過ぎる故に、愛して苦しくなってしまう。あぁ。愛くるしいとはこの事か。  顔がにやけっぱなしの私を、さらににやけっぱなしにさせたのは「平日の朝一番である」ということ。えぇ。独占状態です(爆) 顔がにやけっぱなしの私を、さらににやけっぱなしにさせたのは「平日の朝一番である」ということ。えぇ。独占状態です(爆)5分近くは他のお客様がいらっしゃらなかったので、一緒にお写真撮らせてもらったり、ひこにゃんだけのお写真を撮らせてもらったり、もふもふしたりと、1ヶ月前の新宿イベント時と比べたら考えられない位の触れ合い度に「彦根に来て良かったーーーー!!!!」と腹の底から叫びたくなる。でも大人だから、叫ぶのは我慢(笑) 時間が経過するにつれ、お客様もちらほらと博物館に。 礼儀正しいひこにゃんはその都度、お客様にきちんとお辞儀をしてお出迎えし、博物館入口に誘導。 お客様との記念写真にも素早くポーズ。そのポーズがまたかわいらしく、撮影風景を眺めている周囲のお客様からも「ひこにゃんかわいい!」と声があがる程。何よりレアなのは、正座をするひこにゃんと一緒に写真が撮れることでしょう。 立ち上がったり、正座をしたりと、忙しそうにしているひこにゃんに「彦根の顔」として貫禄を感じずにはいられなかった。  ひこにゃんのお客様お出迎え時間は約30分で、あっという間に10時になっていた。 ひこにゃんのお客様お出迎え時間は約30分で、あっという間に10時になっていた。ひこにゃんはお客様にお辞儀をしながら、自動ドアからロビーに入り、更に博物館の奥へとことこと歩いて帰って行く。その間も後ろを振り返っては手を振ったりお辞儀をしたり。またとことこと歩いては振り返ってお辞儀やカメラに向かってポージング。くーっっっ・・・可愛いヤツめ! この時の私は、自動ドアから先はチケットがないと入れないと勘違い。帰り行く後姿は自動ドア手前からお見送り。 ※チケットがなくても、自動ドアを過ぎたロビーまで入れると気付いたのは、2回目のお出迎えの時(汗) |
| 急いで宿に戻り、旦那を起こして2回目のひこにゃん登場の為に博物館にとんぼ返り。 10時45分頃、内濠到着。 だんだんと観光客の姿が増え始め、屋形船が内濠を優雅に運行していた。  この屋形船は「ゆらっと遊覧 彦根城お堀めぐり」という名称で、築城400年祭開会にあわせ運行を始めたもの。古来彦根城のお堀には水運を利用するための船が行き交っており、この屋形船は江戸時代の絵図面や古写真を基に忠実に再現したそうだ。12人乗りと小柄な船の乗船時間は約50分で、内濠の約3/4を往復運行。一時間毎の夕方16時頃まで運行しており、乗船賃は大人1,200円。 この屋形船は「ゆらっと遊覧 彦根城お堀めぐり」という名称で、築城400年祭開会にあわせ運行を始めたもの。古来彦根城のお堀には水運を利用するための船が行き交っており、この屋形船は江戸時代の絵図面や古写真を基に忠実に再現したそうだ。12人乗りと小柄な船の乗船時間は約50分で、内濠の約3/4を往復運行。一時間毎の夕方16時頃まで運行しており、乗船賃は大人1,200円。道路から水面迄は約80cm程の高低差があるため、水上から眺める景色は、また違ったものなのだろうなぁ。 乗れたら乗りたいが、今この時間はひこにゃん優先である。 |
| 急いで博物館に向かい、今度は内部・自動ドア−内のロビーにてひこにゃんを待つ。ロビーには長椅子(ソファー?)が7脚程並べられ、ひこにゃん待ちらしきお客様の姿もちらほら。 11時。博物館奥の方からコロコロとした鈴の音が・・・・。 ひこにゃんだーーーーーーー!!! (ロビーで待っていた人全員が心の中で叫んだに違いない(笑))  ひこにゃんは両手を振り振り、お辞儀しぃしぃやってきた。あっという間にひこにゃんの周囲に集まる方々。誰からも笑顔が零れ落ち、穏やかでとても軟らかなゆるぅ〜い空気が流れ始めた。 ひこにゃんは両手を振り振り、お辞儀しぃしぃやってきた。あっという間にひこにゃんの周囲に集まる方々。誰からも笑顔が零れ落ち、穏やかでとても軟らかなゆるぅ〜い空気が流れ始めた。ひこにゃんともふもふして「もふもふー!!」と感動する方。 ひこにゃんの正座姿に「正座したぁぁぁぁ!!」とそのカワイさにめろめろになる方。 正座してお辞儀する姿に「・・・お詫び??」「・・・挫折??」「・・・立てなくなっちゃったの??」と一瞬悩まれる方々。←(笑) そして「お辞儀してるー!!」と察してくださる方々(笑)  来る人来る人全員を笑顔にして行く、ゆるキャラひこにゃんの魅力炸裂。 来る人来る人全員を笑顔にして行く、ゆるキャラひこにゃんの魅力炸裂。ひこにゃん周辺のお客様の流れが止ったところで、昨日東京出発前に配付貰いがてら立ち寄った舞浜帝国のお菓子を「みんなで食べてねー♪」と餌付け。 餌に喜んでくれた餅さんは・・・自らお菓子を持ってポージング! まさかポーズしてくれるだなんて予想してなかったので、あまりの可愛さに激写!!! (笑) 立ってポーズ、正座してポーズ(爆) 餅さん可愛い過ぎっス。  お付きのお姉さんに「ひこにゃん、持とうか?」と手を差し伸べられても、餌を体の脇に隠して「いやいや」ともじもじ(笑) お付きのお姉さんに「ひこにゃん、持とうか?」と手を差し伸べられても、餌を体の脇に隠して「いやいや」ともじもじ(笑)しばらくの間餌を手にしたままお客様と記念撮影に臨んでいたので、パーク帰りにも見える餅さんでしたが、ある程度したらお姉さんに餌を託しておりまた。 その後のひこにゃんは、腰から "エアー刀" を抜いて一人殺陣。ちょっと凛々しいひこにゃんは案外機敏に動き、時折お客様を切り(爆)、更に片足で立った!! 私の気分は「ク○ラが立った!!」である。 ちょっとお腹が空き始めた餅さんは、11時30分にお昼を食べに帰って行きました。 |
| 餅さんが帰ってから博物館内を見学する。 まず最初に、、、 この彦根城博物館は明治時代に取り壊された「彦根城表御殿」を昭和62年、復元して建てられた建造物である。建てるにあたっては、彦根城一帯が国の特別史跡(新たな建物を建てる事が規制された土地)に指定されている事から、歴史的な景観を壊さぬよう、江戸時代の御殿を復元する事で許可がおりた。 展示品を飾っている部分は「表(おもて)向き」と呼ばれた、行事や政治向きのに作られた間取りを復元。そして「奥(おく)向き」と呼ばれる「木造棟」には、藩主の生活を中心に作られた部屋と庭を復元している。 博物館内は三脚とフラッシュを使わなければ撮影OKとのことで、要所要所で写真を撮らせて頂いた。こういう時、弱い光りも敏感にキャッチしてれくるデジカメはとても便利だ。 |
 まずは、「井伊の赤備え」(井伊家の甲冑)に迎えられる。 まずは、「井伊の赤備え」(井伊家の甲冑)に迎えられる。ひこにゃんが角のついた赤い兜を被っているのもこの「赤備え」からきており、徳川家康が初代井伊家藩主・直政に武田氏の遺臣を中心とする武将を付けた際、その強さが広く知れ渡っていた武田家の有力武将・飯富虎昌(おぶとらまさ)らの「赤備え」にあやかり「甲冑総てを赤でそろえるように」と命じたのが始り。ここから井伊家の甲冑は代々、藩主から家臣にいたる迄朱漆塗りの物が用いられ、兜には天衝(角)をつけるようになった。実用性を重視した甲冑は他の藩主らに比べて簡素な作りとなってはいるが、当時の工芸技術の粋と機能美を備えており、直政は武田の精鋭部隊や象徴を名実共に受け継いで主要な合戦で戦功をあげてゆく。そして後に「徳川四天王」の一人に数えられ、井伊家は武門の家柄になっていった。  2代藩主の直孝は二度に渡る「大坂の陣」で、この「赤備え」を率いて華々しく活躍しており、上の画像右にある朱色の布に金の井桁が眩しい「朱地金井桁文纏(じゅじきんいげたもんまとい)」は実際に「大坂冬の陣」にて使用された旗印で、桃山時代の作品である。 2代藩主の直孝は二度に渡る「大坂の陣」で、この「赤備え」を率いて華々しく活躍しており、上の画像右にある朱色の布に金の井桁が眩しい「朱地金井桁文纏(じゅじきんいげたもんまとい)」は実際に「大坂冬の陣」にて使用された旗印で、桃山時代の作品である。他にも、馬印や、軍扇、太刀、長刀等が曇る事無く現代でも保管・展示され、「井伊の赤鬼」と恐れられていた代々藩主・藩士の誇りを感じずにはらいれなかった。 |
 続いて能の面や装束の展示室には、15代藩主井伊直忠が大正末年〜昭和初期にかけ収集したもので、新しく誂えたものも含まれていた。 続いて能の面や装束の展示室には、15代藩主井伊直忠が大正末年〜昭和初期にかけ収集したもので、新しく誂えたものも含まれていた。能は、江戸時代に幕府が儀式で行う楽舞とし、諸藩もこれにならい能役者を召し抱えて演能が行われるようになった。 4代藩主井伊直興は55人もの能役者を一斉に召し抱えたそうだが、直興が隠居すると能役者の大半が解雇され、彦根藩の能は衰退していった。直興が55人もの能役者を召し抱えたのは、時の将軍徳川綱吉に従う姿勢を見せる為だったともいわれている。 その後再び藩で能が盛んになるのは、10代藩主井伊直幸・11代藩主井伊直中の代で、最盛期は11代藩主井伊直中の時。博物館中央部に立つこの能舞台を建てたのも、11代直中であった。寛政12年(1800年)の事である。  この能舞台は過去何カ所かに移転されていたが、再びこの地に移築復元。傷みの出ていた床板や一部の柱を新材に交換している。 この能舞台は過去何カ所かに移転されていたが、再びこの地に移築復元。傷みの出ていた床板や一部の柱を新材に交換している。能舞台は当時の配置通り博物館(「表向き」)に囲まれるように建てられ、観客席は屋根のある室内に設置。この400年際開会式で使用されたのが記憶に新しいところだろう。 なお、当時の演能はお抱えの能役者を中心に行われるが、藩士や町人役者など、多くの素人役者も動員される事もあったそうだ。 |
|
続いて「木造棟」と呼ばれる、藩主が生活の場としていた「奥向き」へと向かう。※ココからは外の建物なので、外気に触れます。 |
|
続く展示物は、茶道具、雅楽器、調度品、屏風や掛け軸等の絵画、古文書や典籍等で、15代続く井伊家藩主らの愛でた芸術・芸能や、井伊家代々に続くその功績を目の当たりにする。 博物館ぐるっと一周、足早に回っても約1時間。各作品の展示文を読み、各展示室に置いてある展示解説シートにも目を通しながらだと半日はかかりそうだけれど、歴史のある現物を目の前にできるのだから、その価値は十分あると思う。 |
|
博物館を後にし、遂に彦根城へ!! 彦根の旅 中編に続く |
 観光するには朝早い時間とあって、駅前お城通りも内濠近辺にも人の姿はまばら。駐車している自動車もほぼなく、お城周辺はとてもとても静かで近くの高校からも生徒の声は聞こえない。
観光するには朝早い時間とあって、駅前お城通りも内濠近辺にも人の姿はまばら。駐車している自動車もほぼなく、お城周辺はとてもとても静かで近くの高校からも生徒の声は聞こえない。 能舞台を横目に、一時は井伊藩がその窯を召し上げていた幻の「湖東焼」を拝見。何故幻かというと、明治で途絶えてしまった窯なのである。
能舞台を横目に、一時は井伊藩がその窯を召し上げていた幻の「湖東焼」を拝見。何故幻かというと、明治で途絶えてしまった窯なのである。 各室には当時の部屋の名称プレートが置かれ、その室の用途や位置関係を確認しつつ見学ができる。
各室には当時の部屋の名称プレートが置かれ、その室の用途や位置関係を確認しつつ見学ができる。 更に私的な場所であった奥へと進むと「御客座敷」という、藩主の親しいお客様や親戚をもてなした部屋に突き当たる。
更に私的な場所であった奥へと進むと「御客座敷」という、藩主の親しいお客様や親戚をもてなした部屋に突き当たる。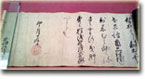 さすがに譜代大名の筆頭であり、将軍を後見する立場にある大老の家だけあってか、古文書の中には豊臣秀吉の書状も見受けられた。こうして様々な時代・事変・歴史をこえ、豊臣秀吉の文字を間近で拝見できるだなんて、不思議な感覚だ。
さすがに譜代大名の筆頭であり、将軍を後見する立場にある大老の家だけあってか、古文書の中には豊臣秀吉の書状も見受けられた。こうして様々な時代・事変・歴史をこえ、豊臣秀吉の文字を間近で拝見できるだなんて、不思議な感覚だ。